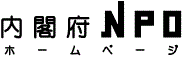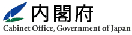事業報告書等
質問一覧
以下の質問一覧を選択すると対応するQ&Aへ移動することができます。
質問と回答
2-5-1 NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。 【第28条3項】
2-5-2 事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として成立後も所轄庁に提出したり、閲覧させたりすることがあるのですか。 【第28条】
事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要がありますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。しかし、NPO法人自身が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行うに当たって実務上有用な書類であるといえるため、経常的に作成することを妨げるものではありません。
2-5-3 事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成されるので、設立当初は備え置く必要がないと考えてよいのですか。 【第28条1項】
事業報告書、活動計算書及び貸借対照表は、設立後最初の決算が行われるまでは作成されませんので、備え置く必要はありません。
しかし、財産目録については、設立の時に作成して備え置くことが義務付けられています(法14)。
2-5-4 従たる事務所がいくつもある場合、すべての事務所で書類を備え置かなければならないのですか? 【第28条1項】
そのとおりです。
2-5-5 法人の事務所における閲覧について、各書類については、いつまでの期間のものを閲覧させればよいのですか。 【第28条3項】
法第28条第3項の規定に基づき、その時点において「事業報告書等」「役員名簿」「定款等」として備置期間内の有効なもの、すなわち「役員名簿」「定款等」は最新のものを閲覧させることとなります。
2-5-6 閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。 【第28条】
2-5-7 法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なることがありますか。 【第28条3項】
2-5-8 謄写に当たって、所轄庁から手数料等を請求されることはありますか。 【第30条】
開示書類の謄写については、請求者本人が行うこととされているので、情報公開制度のように、行政機関が写しを交付する仕組みとは異なります。したがって、所轄庁が自ら謄写行為を行うこととして、当該行為に係る手数料を取ることは不適当だと考えられますが、閲覧・謄写が行われる場所にコピー機等を設置し、実費(コピー代及び紙代等)を徴収することは、当事者間の合意に委ねられることとなります。
2-5-9 届出事項と認証事項をまとめて定款変更認証申請書として所轄庁へ提出した場合、その認証事項について不認証決定がなされると、届出で足りる事項についてもその変更は認められないのですか。 【第25条】
届出事項と認証事項をまとめて申請書として提出した場合、これらをまとめて認証又は不認証の決定がなされます。したがって、お尋ねのケースのように不認証決定がなされた場合は、別途当該届出書事項のみを変更した定款を添えて、定款変更届出書を提出する必要があります。
2-5-10 貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必要がありますか。 【第28条の2】
定款を見た市民や利害関係者にとって当該NPO法人の貸借対照表がどのような手段により、どのような媒体において公告されているかが明らかになる程度に明確に定めていただく必要があります。
具体的には、
- 官報に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「官報に掲載」と記載してください。
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「○○県において発行する○○新聞に掲載」など具体的に記載してください。
- 電子公告の方法を選択する場合は、例えば、「この法人のホームページに掲載」、「内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄) に掲載」など具体的に記載してください。他方、URLまで定款に記載する必要はありません。
- 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置を選択する場合は、例えば、「この法人の主たる事務所の掲示場に掲示」など具体的に記載してください。
2-5-11 貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めることはできますか。 【第28条の2】
公告方法を「A及びBによる方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。
これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかではないためです。
2-5-12 貸借対照表の公告以外にも公告事項はありますが、貸借対照表の公告のみを別の方法とすることを定款に記載できますか。 【第28の2条】
電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの」(法規第3条の2第1項) とは、要するにインターネット上のウェブサイトに公告事項を掲載することをいいます。当該ウェブサイトは、NPO法人自身が管理運営するものでもよいし、第三者が管理運営するものであって当該NPO法人が直接掲載するものや第三者に委託し掲載するものであっても構いません。
掲載については「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く」(法第28条の2第1項第3号) ことが必要ですので、判断に当たっては、例えば、無料で、かつ、事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態にあるのか、法定公告期間中継続して掲載することが可能か、などを踏まえる必要があります。
2-5-14 電子公告の方法として、LINEを使用する方法は含まれますか。 【第28の2条第1項第3号、法規第3条の2第1項】
SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供されるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービスごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。
例えば、あるNPO法人がLINEのトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を閲覧するには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これは、「事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えませんので、LINEは電子公告の方法としてふさわしくないと考えられます。
2-5-16 貸借対照表の公告の方法として官報又は日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合、貸借対照表の「要旨」(法第28条の2第2項)とはどのようなものをいうのですか。 【第28の2条第2項】
掲載金額の単位については「千円」とするなど、適切な単位をもって公告するものをいいます。
また、掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具体的事情に応じて、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載した事項を公告するものをいいます。
2-5-17 貸借対照表の公告について、内閣府NPOポータルサイトに掲載する方法を選択した場合、費用は発生しますか。また、どのような手続きが必要ですか。 【第28条の2】
内閣府NPOポータルサイト(https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/)に掲載する場合、費用は発生しません。内閣府NPOポータルサイトに掲載する手続きとしては、①NPO法人において新規ユーザー登録、②内閣府から法人の主たる事務所の所在地宛てに法人確認書類が郵送される③サイトにログインし、公告欄にPDF化した貸借対照表を掲載、という手順を踏んでいただく必要があります。
2-5-18 内閣府NPOポータルサイトの閲覧書類欄に、貸借対照表のデータが掲載されていますが、貸借対照表の公告の方法を電子公告と定めている場合、これをもって法28条の2に規定する公告とすることはできますか。 【第28条の2】
内閣府NPOポータルサイトの閲覧書類欄は、所轄庁において独自の判断で書類の掲載をしており、これをもって法28条の2に規定する公告を行ったことにはなりません。あくまで法人自身によって、マイページの公告欄に掲載いただく必要があります。



 |
|