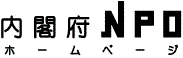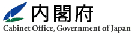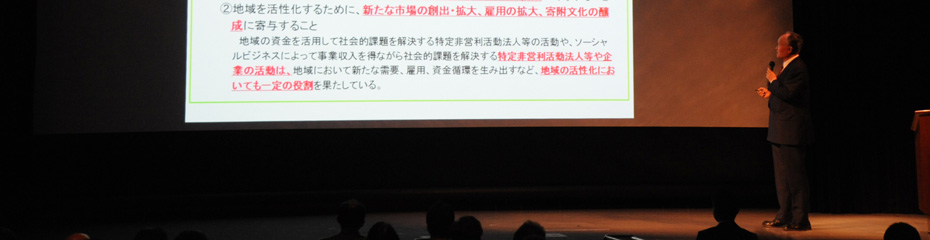共助社会づくりシンポジウム 基調講演 3
基調講演 「共助社会づくりの推進に向けて」
目次
3.共助社会づくりの推進に向けて
共助社会づくり懇親会では平成25年6月より人材・資金・信頼性の向上の3つのワーキング・グループに分かれて、深く議論を行ってきました。
まず、人材面の課題についてです。人材の育成については、NPO法人・市民の側も人材面に課題があることを認識しています。特にビジョンの提示、事業計画の策定等の専門的なノウハウを持つマネジメント人材が不足しています。また、スタッフなどマネジメント人材以外の人材育成も重要です。各専門分野に特化した内容の専門講座を実施することや、マネジメント人材への伴奏型支援の実施、成果評価を行いその評価結果を発表する公開セミナーの実施も必要です。
私は、中京大学の総合政策学部で教えていますが、最近、NPO等でもインターンシップを引き受けて頂いています。学生にとっては非常に人気が高く、インターンシップ後の感想では、その後の大学生活でがんばる自信がついたと言う学生も多くいます。大学の中で、NPO等やソーシャルビジネスに関する講義が充実してくるといいと考えています。
人材の流動化に関しては、企業、大学、行政、中小企業の人材の交流は進んでいません。企業とNPO等がパートナーシップを組むことは増えてきていますが、人材がお互いの組織の間を行き来して行動することはまだまだ進んでおりません。流動化を促進するために企業のニーズに応えるような事例集やキャリアモデルを発信することが考えられます。
また、中小企業のソーシャル化という点では、中小企業から出向し、NPO等で一定期間勤務することでマネジメント能力の向上や新しい事業の発掘にもつながると思います。また、NPO等の事業者に、大学の教員や経済団体等の専門家として、現場を見ながら活躍していただくなど、キャリアパスを作ることが大事であると考えます。
次に資金面の課題があります。まず、寄附・会費の納付環境が整っていません。世論調査によれば「寄附をしたい」と回答した人は約23%、寄附はNPO等の活性化にとって非常に大事ですが、ちょっと少ないと思います。
市民ファンドは最近になって増えてきていますが、多くの団体は市民から十分な資金を集めることができておらず、地域に一定の影響力を持つ団体の数も限られています。報告書では1県に1つ程度の市民ファンドの創設されることを期待していますが、現時点では全国に40団体程度の市民ファンドがありますが、全国的に増えているという状況にはありません。
そして、NPO等への融資の拡大の問題があります。これは金融機関とNPO等との間の関係です。現在、NPO等の資金調達は個人からの借り入れが7割を超えています。この原因の一つに金融機関におけるNPO等に対する理解の不足があります。NPO等への融資はデフォルト等が低いにも関わらず、一般的にはリスクが高いと誤解されています。
そして、金融機関、自治体、コンサルなどから個別に支援を受けていますが、面的な支援の仕組みが構築されていません。この問題に対してはまず手始めに、行政、地域金融機関、商工会議所、商工会、税理士、公認会計士、大学、専門学校等の学術機関、NPO等、市民ファンド、NPOバンクなどで課題の共有を図る共助社会の場を作り、連携していくことが大事であると考えます。
最後に信頼性の向上に関する問題があります。これには四つのテーマがあります。
第一に情報開示のあり方です。寄附者が求めている情報が適切に開示されておらず、NPO等に対する理解が進まず、その結果、寄附の相場観が市民の間で醸成されていません。解決に向けた方向性として、分かりやすい事業報告書、寄付者向けの年次報告書の作成の促進や各種調査結果を広くNPOと共有することが考えられます。
第二に情報基盤の問題です。現在、NPOに関する民間のデータベースは複数あります。NPOはそれぞれに登録する必要があり、負担になっています。そして、それぞれのデータベースは更新時期が違うため、最新情報が把握しづらくなっています。また、行政が有するNPOに関する情報へのアクセス環境も不十分です。内閣府のNPO法人ポータルサイトの情報は民間のデータベースとやり取りができないため、民間の情報とリンクさせることができません。また、NPO法人と公益法人はそれぞれ別々のデータベースで運用されており、共通化できていません。これはまさに政府が取り組むべき問題です。
第三に会計基準の問題です。NPO会計基準が作られました。しかし、企業と違ってNPO法人においては、しっかりと会計処理ができる法人は少なく、NPO会計基準の一層の普及と法人の会計処理機能の向上による制度の充実が必要です。
第四として、NPO法人への指導・監督があります。一部の信頼を損なうような団体、休眠法人の放置などがありますが、これも行政の役割が大切です。改正NPO法の施行後3年を目処とした検討にあわせて、運用課題を整理・検討することとされています。
日本のNPO等についてはテイクオフしたと思っています。ただ、テイクオフしたけれども、まだ発展途上であり、しかし、発展途上ではあるけれども、急速に成長している段階であると思っています。少し言い方は悪いですが、NPOは「それぞれが好きな楽器を持ち寄って、好き勝手に吹き鳴らす」という部分が大事だと思います。それが強靭な国の力になるのではないでしょうか。政府においては、いま紹介したような方向性に向かって政策を考えていただきたいと思います。



 |
|